2017年08月23日
価標と原子価の違いって・・・?
今回は構造式を授業で扱うときによくある質問について。
化学式には分子式、組成式、イオン式、電子式、構造式・・・といった
色々な表示法がありますが、そのなかで構造式を説明する教科書の
文中に「価標」と「原子価」という用語がでてきます。
この二つの用語は何が違うの?・・・というのが今回取り上げる内容です。
分子の構造式がしっかり書けることが大切であり、
この用語の違いがはっきりとわかっていないためにミスしてしまう
問題はセンター試験レベルではほとんどないと思いますが
正しく用語を使えるようになるために意識して使い分けましょう。
さてさて、分子を構造式で表示するとき、
1組の共有電子対による共有結合(単結合)を1本の線で表します。
この線を「価標」といいます。
2組の共有電子対による共有結合(二重結合)なら2本、
3組の共有電子対による共有結合(三重結合)なら3本の価標で
それらの結合を表現するというわけです。
例えば、水分子の構造式であれば H-O-H
二酸化炭素分子の構造式であれば O=C=O と表示します。
このとき、水分子内には2本の価標があり、
二酸化炭素分子内には4本の価標がある、と言えますね。
では原子価と言ったときにはどうとらえるのでしょう。
「原子価」とは「分子内の一つの原子から出ている価標の数」です。
ようするに分子全体ではなく、あくまで分子の中の一つの原子に
注目して話したい時に用いる用語と言えるでしょう。
例えば先の2つの構造式の中の各原子であれば、
水素原子の原子価は1、酸素原子の原子価は2、
炭素原子の原子価は4、となります。
原子の原子価は分子内でその原子から出ている価標の数であり、
それはその原子がもともと持っている不対電子の数と等しくなります。
まとめると・・・、
分子全体をとらえて
結合の共有結合の本数を話題にするときには「価標」、
原子一つをとらえて、
そこから伸びる共有結合の数を話題にするときには「原子価」、
・・・ということですね。
ちょっとした違いですがこういった用語を意識していくと
高校化学全般の理解も深まっていくものです。
それでは今回はこの辺で。頑張れ受験生!
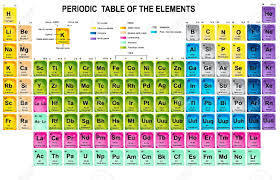
化学式には分子式、組成式、イオン式、電子式、構造式・・・といった
色々な表示法がありますが、そのなかで構造式を説明する教科書の
文中に「価標」と「原子価」という用語がでてきます。
この二つの用語は何が違うの?・・・というのが今回取り上げる内容です。
分子の構造式がしっかり書けることが大切であり、
この用語の違いがはっきりとわかっていないためにミスしてしまう
問題はセンター試験レベルではほとんどないと思いますが
正しく用語を使えるようになるために意識して使い分けましょう。
さてさて、分子を構造式で表示するとき、
1組の共有電子対による共有結合(単結合)を1本の線で表します。
この線を「価標」といいます。
2組の共有電子対による共有結合(二重結合)なら2本、
3組の共有電子対による共有結合(三重結合)なら3本の価標で
それらの結合を表現するというわけです。
例えば、水分子の構造式であれば H-O-H
二酸化炭素分子の構造式であれば O=C=O と表示します。
このとき、水分子内には2本の価標があり、
二酸化炭素分子内には4本の価標がある、と言えますね。
では原子価と言ったときにはどうとらえるのでしょう。
「原子価」とは「分子内の一つの原子から出ている価標の数」です。
ようするに分子全体ではなく、あくまで分子の中の一つの原子に
注目して話したい時に用いる用語と言えるでしょう。
例えば先の2つの構造式の中の各原子であれば、
水素原子の原子価は1、酸素原子の原子価は2、
炭素原子の原子価は4、となります。
原子の原子価は分子内でその原子から出ている価標の数であり、
それはその原子がもともと持っている不対電子の数と等しくなります。
まとめると・・・、
分子全体をとらえて
結合の共有結合の本数を話題にするときには「価標」、
原子一つをとらえて、
そこから伸びる共有結合の数を話題にするときには「原子価」、
・・・ということですね。
ちょっとした違いですがこういった用語を意識していくと
高校化学全般の理解も深まっていくものです。
それでは今回はこの辺で。頑張れ受験生!
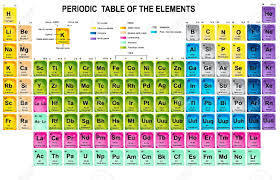
Posted by ミーケン。 at 09:42│Comments(1)
│受験
この記事へのコメント
分かった!
Posted by っk at 2023年02月23日 15:49









